
うどん、好きですか?
私は好きです~
香川県に仕入れにいくと
必ず食べてきます。
コシがあってとても美味しいんです。
毎週食べに行けたら。。。と
思いますよ。
かと言って大阪でもうどんの美味しい
お店もあるんですけど(笑)
なぜ、うどんのお話かって?
そうそう!
昨日つまらないと言ってあなたに聞いてもらった
じゃないですか、天然娘の話。
ようやく言ってくれました。面白い事を(笑)
朝の水やりの際、
「お母さん!盆栽がうどん病になった!」
でたっ!!!
ご存知ですか?うどん病(笑)
そうです、うどんこ病のことです。
朝からスッキリ!昨日までのモヤモヤが
吹っ飛んだようでした。
で、うどんこ病なんですが
結構しつこい病気なんですよ。
この時期によく発生するので
今日はこのお話を。
うどんこ病・・・
葉や新芽などに小麦粉(うどん粉)をかけたように
白いカビが生えます。被害が進むと全体が白いカビで
覆われて葉や若い茎が白色のカビで覆われて葉が変形したり
新芽が伸びなくなったり、生育が悪くなったりします。
ひどい時は枯れてしまうこともあります。
20度くらいで湿度が低いと繁殖しやすくなり
初夏と秋口に多く発生します。
きっちりと除去しないと来年またうどんこ病になるという
恐ろしい~伝染病です。
恐ろしいは言い過ぎですが(笑)
枯れてしまわないよう気をつけなければいけない
よくある植物の病気です。
日常の防除としては混みあった枝葉を剪定したり
風通し、日当たりを良くして落ち葉などを早めに
取り除くようにします。
あっ!大事なことを言い忘れるところでした。
うどんこ病になっていた切った葉や茎の部分は
必ずゴミで処分してくださいね。
その辺に置いておくと風にのってまた広がります。
一度発生するとカビは発病部分とともに土の中で
越冬し、翌春に増えて再び伝染しますので
除去の後、きっちりと予防をしないと
毎年うどんこ病になってしまいます。
早めの処置をして予防の薬剤散布、乾燥すると
発生しやすいので、水やりの際は葉水も忘れずに
してください。
また、チッ素肥料を一度に施し過ぎると病気が
発生しやすくなります。
今、あなたの頭の中はきっと予防しなきゃ!と
なっています?
気になる薬剤散布。
サンヨールやベニカスプレーなどがうどんこ病に
良く効くようです。
発病した部分を取り除いた後、
予防として散布していただくといいです。
いきなり真っ白になるわけではないので
葉がちょっと白い粉がついてないかな?と
水やりの前に観察してください。
早期発見が伝染を起こさないためには
必要です。
それと、ならないようには
やはり、日常の管理。
環境が病気にさせてしまうことが
よくありますので、風通しや日当たりなどを
よく考えて置き場所を決めることですね。
うどんこ病の発生しやすい樹木は
アジサイ、梅、もみじ、バラなどです。
葉に黄色いてんとう虫がいたら
うどんこ病のカビを食べてるので捕らないで
菌を食べてもらいましょう。
病気も知れば怖くなくなります。
知って安心して対処してください。
あ~お腹空いた
今日はうどん食べようかな(笑)



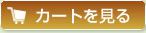







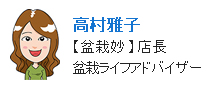
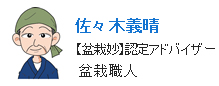
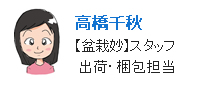
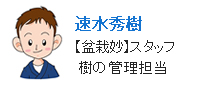


静岡の大久保です。さっそくご返事頂きありがとう御座います。さっそく商品一覧からサンヨ-ルを注文させてもらって、ためしてみます。有り難う御座いました。